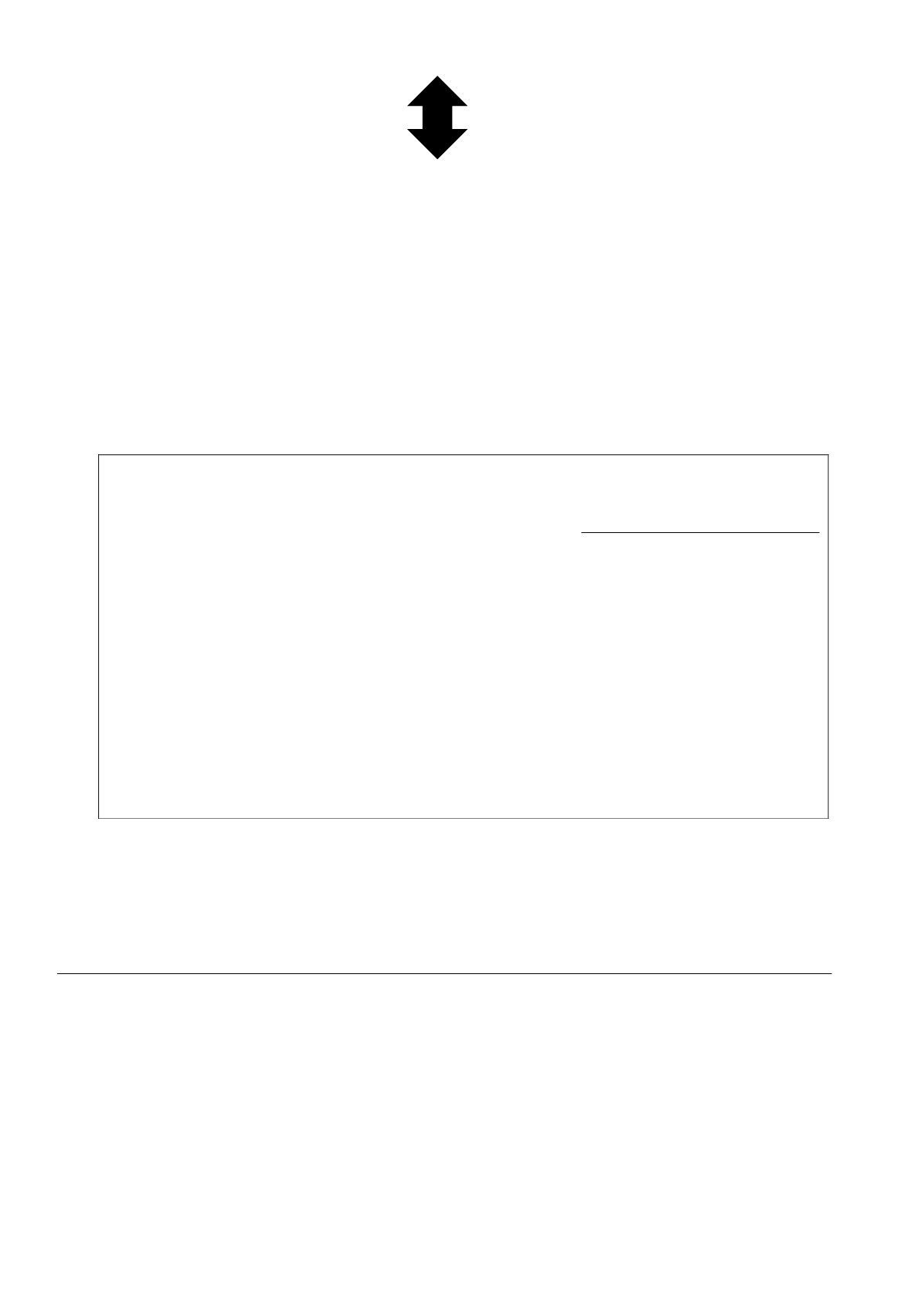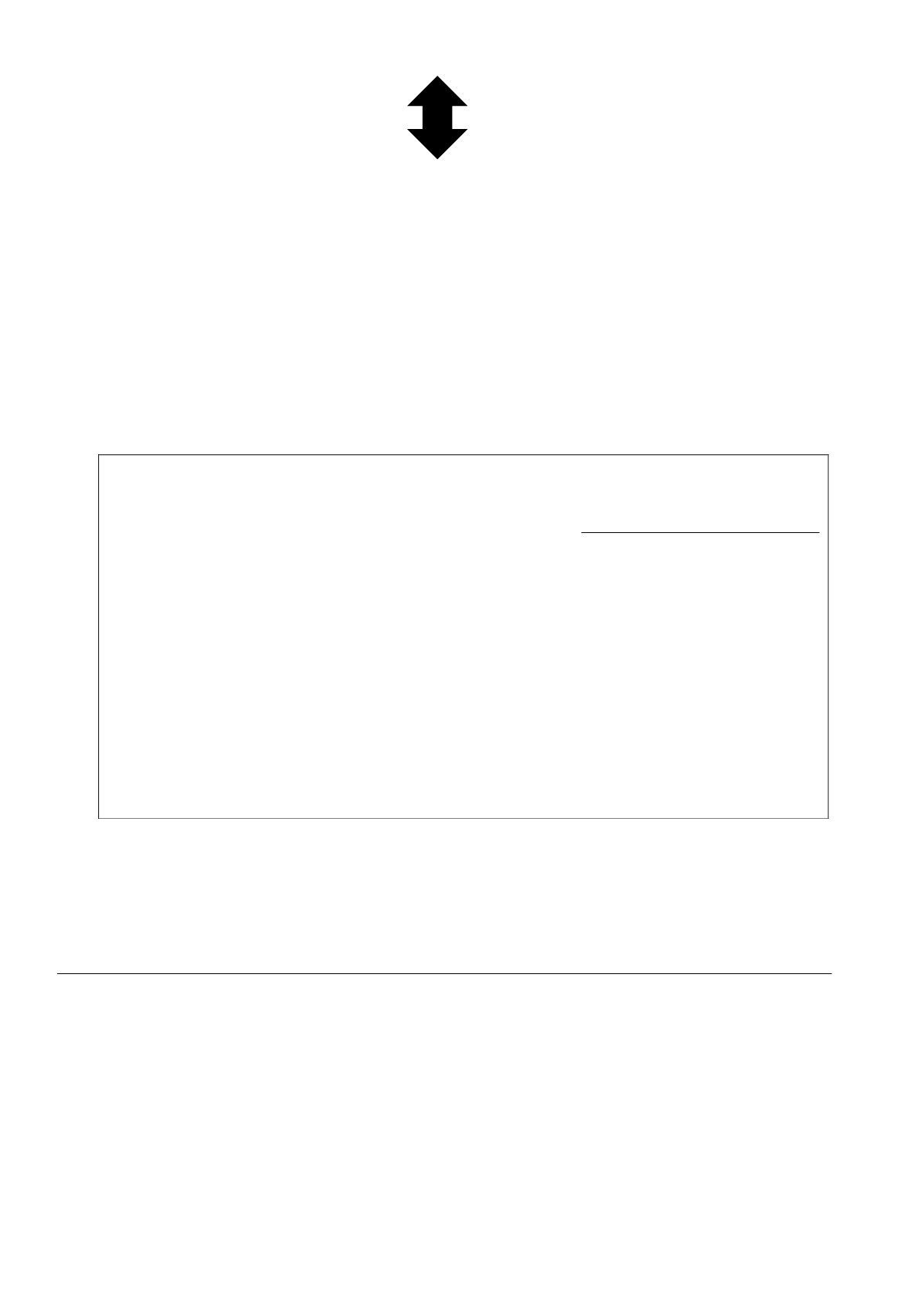
5
一方で・・
この攻防の展開に必要な「いつ・どこに打てばよいか」という状況判断に関わる「隙のありか」を理解させ、
かつその打突機会を意図的・戦略的に創り出し有効打突を奪えるようにするための教材づくりとして岩田ら
(2009)
の先行実践研究がある。
【岩田ら
(2009)
の先行研究】
岩田ら
(2009)
は、「隙のありか」を理解させ、かつその打突機会を意図的・戦略的に創り出し有効打突を奪え
るようになるための教材づくりにあたり、以下の
2
点をテーマに約束練習のゲームを開発し、授業実践を行っ
た。
・「一太刀で攻め、相手の変化を予測し、判断して二太刀を打つことができる」
・「一太刀、二太刀についてチームで考え、工夫し、その技を試合で生かすことができる」
以下が約束練習である。
【本時では】
この実践の課題として「相手に変化がないので、いつ仕掛けてよいかわからない」がある。このことについ
て岩田
(2009)
は、相手に隙ができるのを待っていることの問題点を挙げている。
そこで、今回のつくば実習では、
◎Bが竹刀を抱え込むように崩れる→Aは小手を打つ①削除→※Bが動かない→Aは払って面に変更し、
相手が崩れない場合の「隙」についても作れるように、ルールを変更した。また、今回の対象学年である中学
校第
1
学年で小手を扱わないことも理由の一つとしている。
(ゲーム②)
<
ねらい
>
相手の崩れに応じた技の選択
・自らの打突に対して相手が崩れ、その際に生まれる隙に応じて行使する。また、自分で相手の隙を作って打つ。
<
約束課題
>
A:打ち役 B:打たせ役 C:審判
・一足一刀の間合いからスタート。 ・Cの「
1.
本目!」「
2
本目!」という掛け声によって、Aが攻め込む。
・Bはそれに対し、崩れる(守りの姿勢をとる)
◎Bが面を避けるように崩れる→Aは胴を打つ ◎Bが竹刀を抱え込むように崩れる→Aは小手を打つ
◎Bが後方に退く→Aは追い込んで面を打つ。
※
1.
ゲーム
5
本。
1.
本になる技を打てた回数を得点化する。
〇BはAの攻めに対して素早く防御等の体勢になれるようにし、Aは隙の判断を速めていけるようにする。