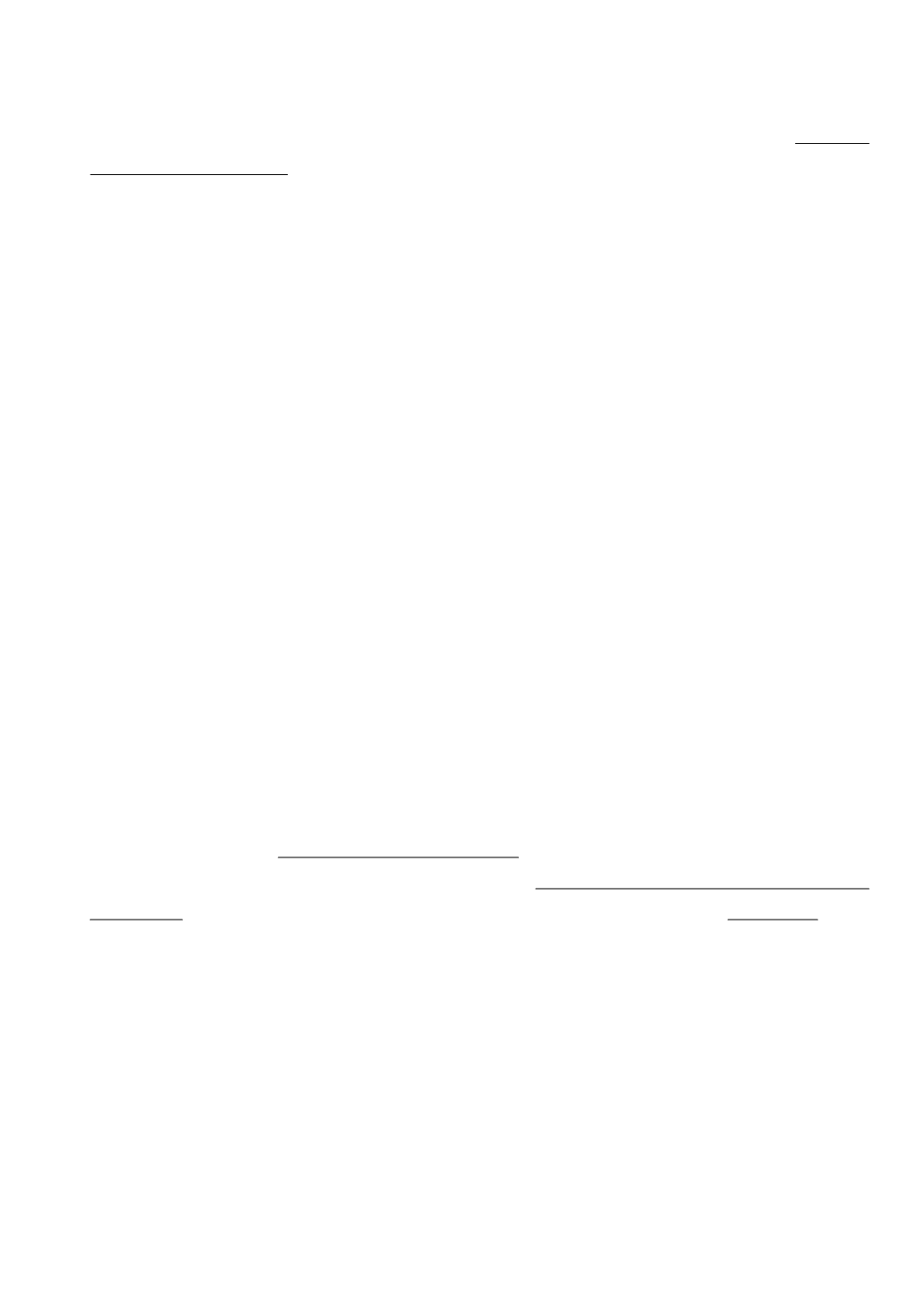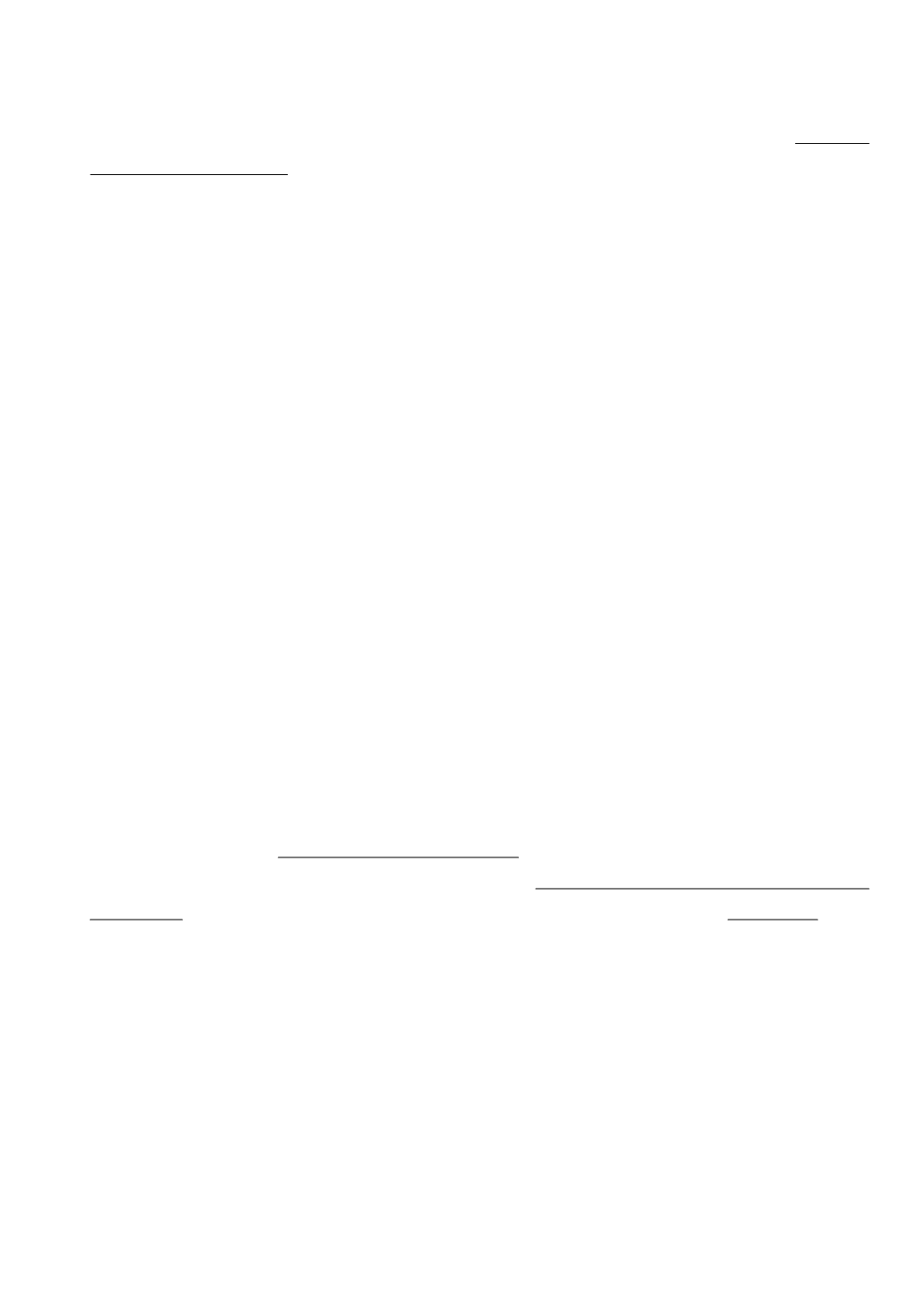
(3) 中学校における「武道」実施状況について
武道必修化に合わせて2012年に文部科学省が全国の公立中学校を対象に行った調査では、柔道を実
施する中学校は 64.1%であり、剣道(37.6%)、相撲(3.4%)に比べて非常に多くの学校で実施さ
れていることが明らかとなっている。
(4) 単元構成・教材作成の意図
柔道活動中における重大な事故の問題は、現行の学習指導要領の実施を契機に多数報道され、社会問
題となった。平成24年度より中学校において新学習指導要領が全面実施され、武道が必修化されたこ
とによって、今までよりも多くの生徒が柔道の持つ潜在的な危険性に晒されるおそれがあり、柔道授業
における事故の危険性が懸念されている。また、実際の指導現場において、教師は、授業時間や授業環
境、教師の指導力に対する不安など様々な制限や障壁があると野瀬(2009)や
鹿屋体育大学生涯スポーツ
実践センター
(2010)は報告している。一方、花田(1985)や高橋(1986;1987)は生徒が柔道に抱い
ているイメージに関する調査を実施した。その結果、中学生・高校生男子において柔道は「男らしい」
「たくましい」という形容詞に代表されるように身体の鍛錬効果についての認識は高いものの、「激し
い」「痛い」というイメージも強く、生徒においては非好意的・逃避的であるとしている。これらの研
究成果から、授業においては柔道を専門としない保健体育教師においても安全が確保でき、より効率の
良い授業の展開について考察していく必要があると考えられる。さらに、その授業計画で用いる教材は
生徒にとってわかりやすく、面白く感じられ魅力のあるものである必要があると言えよう。
そこで、本単元では、生徒が分かりやすく面白いと感じて取り組める教材を用いながら、生徒の柔道
への負のイメージを払拭できるよう、受け身を中心とした学習からスムーズに投げ技に入るよう構成し
た。通常、学校現場では、安全上の配慮から、単元の前半又は第1学年は固め技から入るような授業が
多く見られる。しかし、ここではあえて、受け身の動作に器械運動の要素を取り入れながら、安全上の
学習を踏まえスムーズに投げ技へ移行できるような構成にし、受け身から立ち技への単元を提案したい。
授業を行うにあたり、安全かつ効率よく進行するために、また、生徒にとってわかりやすく面白いと
感じられるために、縦や横に回転する、高さのあるところから身体を操作しながら勢いを制御するなど、
共通した運動特性を持つ器械運動を活用した準備運動の提案を行う。
さらに、授業内容の効率化と一層の充実を図るために、受身の学習から投技の学習への発展を重
視した教材を工夫することを提案する。そして、学習を促進する教具の工夫として「人体図」の活用
の提案も併せて行う。「人体図」は、教師が指導したい身体の意識ポイントの視覚化を図ること、教師
と生徒の共通認識を深めることをねらいとする。
(5) 授業者の授業観
本授業では受身の習得、つまり受身の動きを身に付けることが大きな課題である。そして今回の授業
で取り組む前受身では上半身を前腕で支える姿勢づくりが、後受身では背中に丸みを持たせる姿勢づく
りが、横受身では頭を起こす姿勢づくりがそれぞれ必要とされる。したがって授業ではこれらを中心に
指導を行いたい。
姿勢づくりを重視した動きを身に付ける指導法として、器械運動を対象として意識するポイントを焦
点化・視覚化する指導法がある。この指導法では運動に必要な身体の意識ポイントを焦点化・視覚化す
ることによって、よりよい運動・動き方を導く指導法である。この考え方を参考に本授業に部分的に取