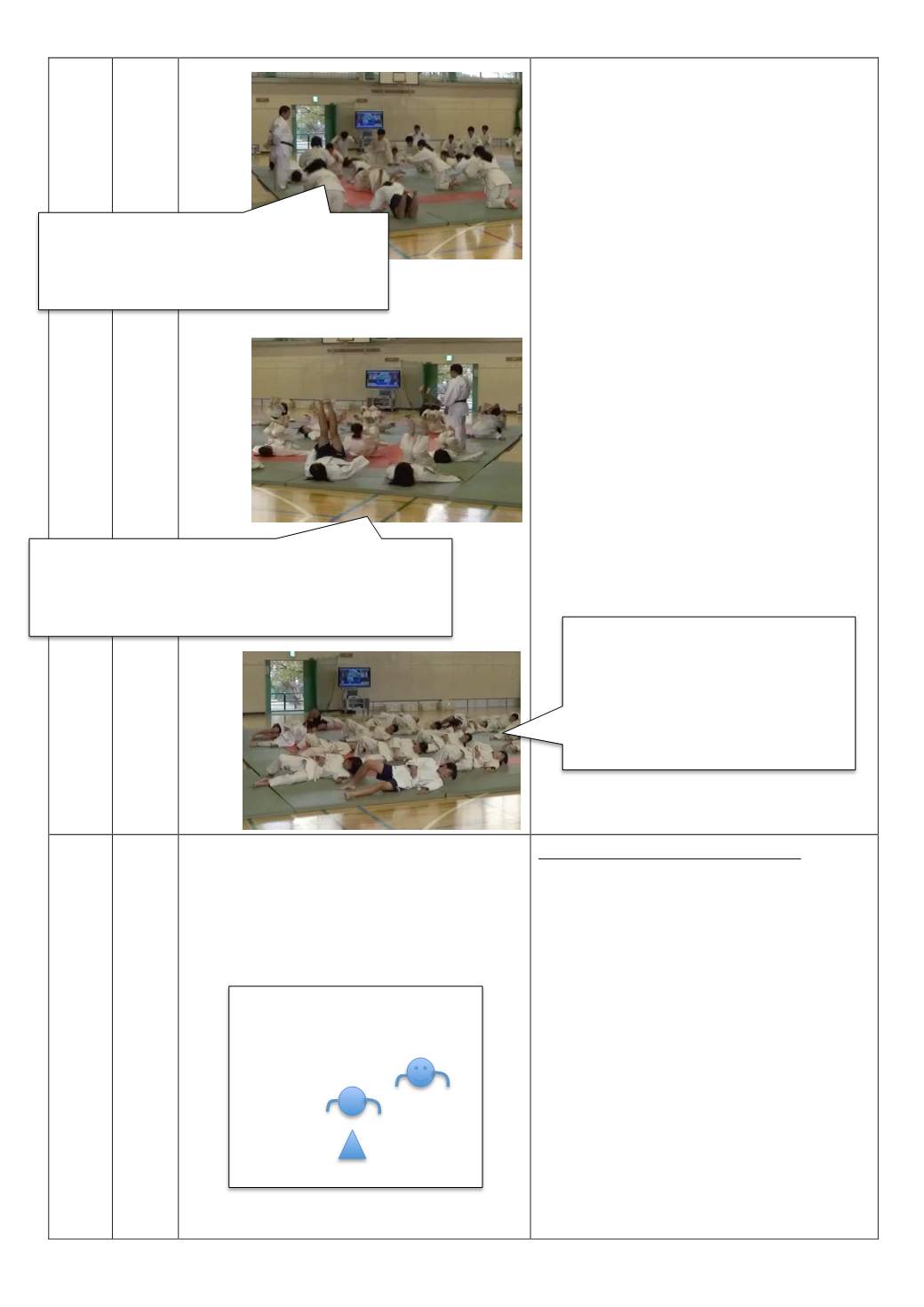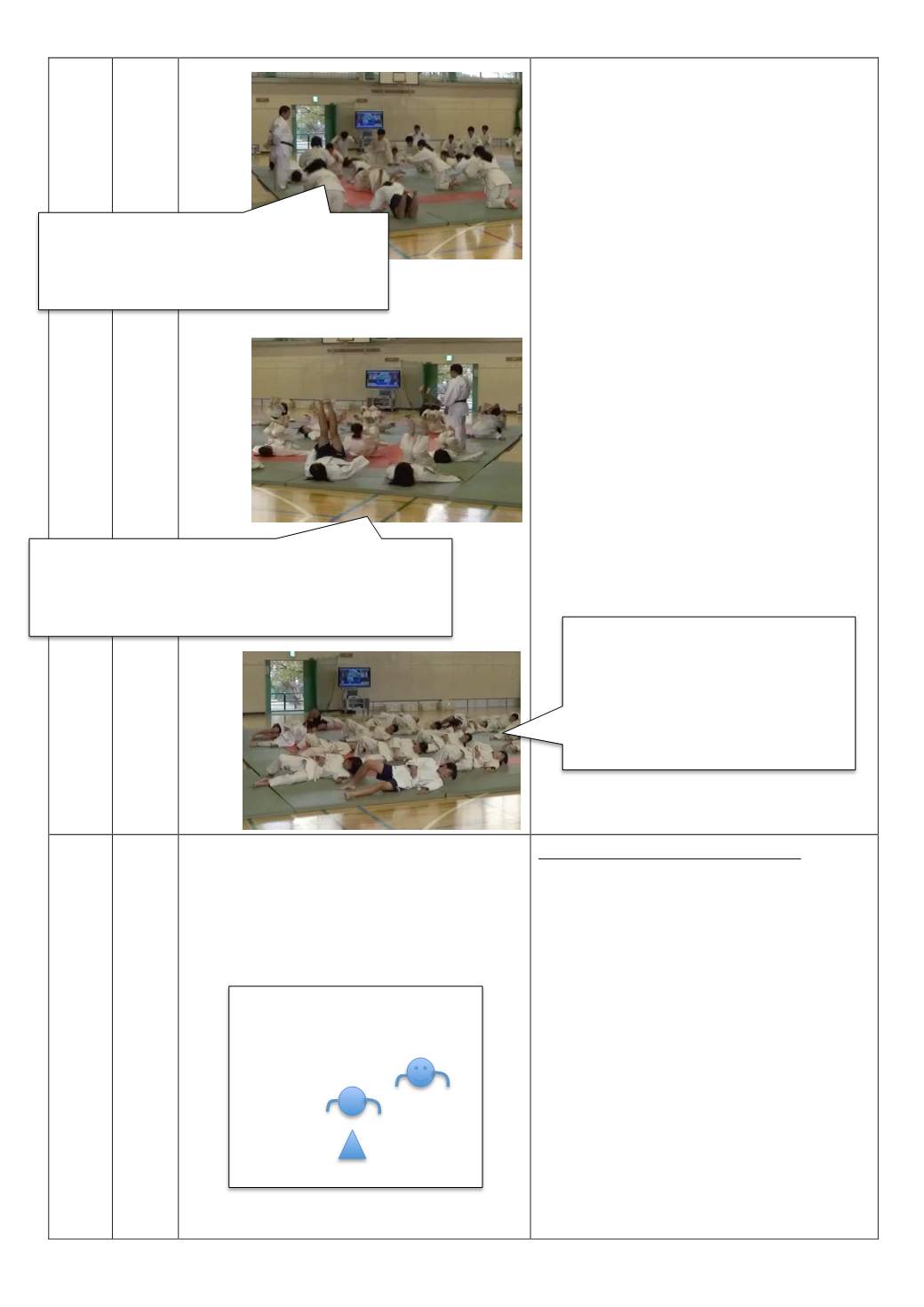
・後受身の復習(蹲踞から)
・横受身の復習(仰向けから)
後に、人体図で説明した意識するポイント
を踏まえて多くの生徒ができていない点
を
1
つずつ指摘して、改善を促す。後受身、
横受身も同様に行う。
•
大きくはっきりと数を数える。また、指摘
する際は、前受身では「縦・横のアーチ」
を、後ろ受身では「縦のアーチ」を、横受
身では「横のアーチ」を強調して指導する
ようにする。
※ 技術的なポイントや専門的な助言について
の詳細は教材案に示した。
展開
2
18
分
(7
分
)
6.
手押し相撲を行う。
•
3
人組をつくる。
•
2
人が向かい蹲踞の姿勢で押し相撲をする
•
負けるか
3
回続けて勝ったら交代する。
•
5
分間対戦を行う。
(教材案
2
—③および
3-
③を参照)
•
受身を行った隊形からすばやく背の順で
3
人組をつくる。柔道の特性上、同性の組を
つくるようにする。その場合に余る生徒が
いた際には
4
人組とする。
•
2
人が対戦している間、もう
1
人は周りと
ぶつからないように安全を確保するとと
もに、受身が正しくできているかを見る。
受け身に必要な身体の意識ポイントに注
意しながら行う。
•
ゲーム性の強い教材を採用ため、周囲の安
全と規律を維持するような声かけを積極
的に行う。
前後左右に十分な間隔を取る。狭いときは互い違いになる
など、安全を配慮した工夫を行う。畳を打つ位置は体から
45
度くらい開いた位置で叩く。また指は閉じる。
膝立ちの状態から前に倒れる。顔の前で“三角
形の窓”を作り、それを崩さないようにして、
指先から肘までで畳を叩く。
横受身では手だけでなく、脚でも畳を
打つようにする。
そのために、打つ手と同じ側の脚を伸
ばす。逆の足は立てて、畳を底辺、膝
を頂点に三角形を作るイメージ。
受
取
ガード